第2回 翻訳者が伝えるべきもの
自分では流行に乗るタイプの人間ではないと思っているのですが、最近よく聞く「突発性難聴」という病気にかかりました。ネットの情報によると、原因も特定されていない病で、かかった人の30%は治らないとか。昔、家族がガンで入院していたとき、○年生存率○%という中で生きるというのはどういうものだろうかと思いをめぐらせてみたものですが、今回それを、命に関わらない、薄められた形で実体験できた気がします。
その結果分かったのは、想像していたとおり、客観的な統計確率と、当事者としての感覚は別物だということです。つまり、70%は良くなると言って も、私個人にとっては、良くなるかならないか、100%か0%かどちらかなのです。まあ、重症度とか後遺症とか考えれば、100%か0%かと決めつけるほ どでもないのですけれど、原理的な話としてですね。で、今回は、翻訳の場合も、客観的な100%と翻訳者自身の100%とは別物だというお話です。
翻訳不可能論について
正しい翻訳というものがそもそも可能か、という話になったときに、必ず引き合いに出されるのがTraduttore, traditoreというイタリアの諺です。「翻訳家は裏切り者」。完全な翻訳などありえないという意味で使われます。私は、基本的にこの意見に賛成して います。すべてにおいて100%の翻訳は、原理的に不可能だと思います。
こんなことは、実際に翻訳をされている方は実感として先刻ご承知でしょうが、学習者の方は、うまく伝えられないのは「自分の力が足りないからだ」とだけ思っておられるかもしれません。もちろん力不足という問題は常にありますが、それだけではないのです。
前回、力説したとおり、翻訳というのはコミュニケーションの一つの形です。人が人に何かを伝えるとき、伝わっていくものは一つではありません。言葉 以外の視覚的要素もありますし、言葉が媒介するものに限定しても、意味内容もあれば、言葉の調子もあります。言葉が表す音もリズムもコミュニケーションの 一部です。こういった多層的な情報を、すべてまとめて他の言語に移し替えることは、ふつうはできません。
例えば先ほどのTraduttore, traditoreです。「翻訳家は裏切り者」と訳せば、とりあえず意味は伝わります。この文章の言語関係のおかげで、翻訳不可能論といった背景の文脈も ある程度伝わるでしょう。けれども、そもそもこれが諺として成り立っているのは、トラドゥットーレ、トラディトーレという語呂があってこそなのです。「翻 訳家は裏切り者」ではこの言葉のリズムは伝わりません。言語学者の金川欣二さんは「訳者はヤクザ」と 訳されていますが、これだとかなり地口っぽい感じがします。けれどもどうでしょう。私がこの文章の中で「訳者はヤクザ」を使ったなら、意味的に、翻訳不可 能論の説明からはかえって遠ざかってしまうのではないでしょうか。あちらを立てればこちらが立たず。これが、「すべてにおいて100%の翻訳は不可能」と いうことの実態です。
私の頭の中では、この事態は下のようなイメージになっています。
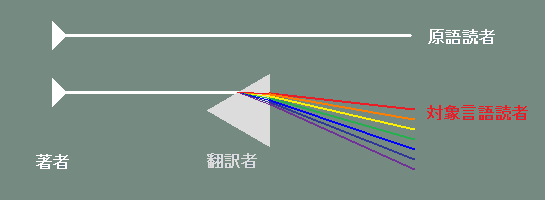
言葉というのは白色光のようなもので、いろいろな色の光が混ざり合っています。ところが翻訳というプリズム を通すと分光してしまい、読者には赤い光しか(あるいは青い光しか)届かない。翻訳者の力量が高ければ、屈折率を低くして赤から黄色までまとめて届けるこ とができるかもしれません。(逆に、最初から赤い光を通さないプリズムを持つ偏った翻訳者もいるかもしれません。)けれども、言語という媒体の密度が異な る以上、もとの白色光のままで読者に届けることは難しいのです。
何を伝えるべきかの判断で考慮すべきこと
翻訳者は、できるだけ光を拡散させないようにするべきですが、それに限界があるとなると、あとできることは、プリズムの置き方を変えて、赤い光を届けるか、青い光を届けるかを選択することです。
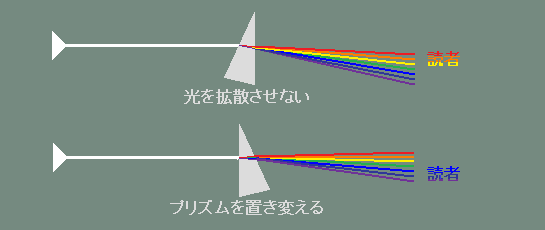
意味内容を伝えるのか、味わいを伝えるのか。こういった悩みは文芸翻訳だけの問題だと思われるかもしれませ んが、ニュースのように事実の伝達が絶対条件である翻訳でさえ、その記事を書いた記者の姿勢や意図というものが文章に反映しているものです。その色合いを 捨てて事実だけを訳出するのか、あるいはその報道の姿勢を明確にするのか。翻訳者は(あるい編集者を含めた翻訳媒体は)、それを判断しなければなりませ ん。
そこで問題になるのは、判断基準です。もちろん、翻訳するものが小説なのか、報道記事なのか、技術文書なのか、ケースバイケースで判断の仕方は違ってきます。けれども考慮すべき要素はどの場合も2つ。「著者の意図」と「読者の立場」だと、私は考えます。
何にせよ、著者が読者に伝えようと意図していることを尊重するのが第一だというのは、翻訳という営みの暗黙の前提です(暗黙であるがゆえに忘れられ がちですが)。ということは、翻訳者は著者の意図を推し量れるようでなければなりません。そのためには、著者と、ある程度「文化」を共有している必要があ ります。推し量る、と書きましたが、著者の意図と言っても、あくまで「翻訳者が想定する」著者の意図に過ぎません。私も場合によっては原著者に問い合わせ をすることがありますが、一般論としては、「著者が想定する読者が推し量れるレベルでの著者の意図」(ややこしいですけど)が読み取れれば十分と言えま しょう。そのために私たちは、いろいろ調べ物をしたり、相手方の文化に触れようとしたりするのです。
そうして、翻訳者は著者の意図の優先度を推し量ります。テキストの中にジョークが挟まっていたとしましょう。そのジョークの中身が大切なのか、それ とも、そこで読者を和ませることのほうが著者にとって大切なのか(その場合、中身を少し変えても笑いを取るという判断もありえます)。たとえばそういうこ とです。
さて、ところが翻訳の場合、読者が「著者の想定する読者」と重ならないこともあります。もう少し厳密に言うと、「著者の想定する読者」と「翻訳が想 定する読者」の相違です。ジョークの例で言いますと、著者はそこで和ませることでさらに読者を引きつけようとしているのかもしれません。ところが翻訳対象 文化では、そういう文脈で笑いを入れることは、単に不真面目と受け取られるだけかもしれません。
著者にとって、読者を引きつけることが第一であると訳者が判断したなら、そのジョークを外すという「翻訳」をする判断もありでしょう。けれども読者 は、原語の、たとえば米国の文化をある程度理解していて、それはそういうものとして受け取る、あるいはむしろ積極的に米国文化の文脈でテキストを読もうと しているかもしれません。訳者がそのような読者を想定しているのなら、逆に、多少ぎこちなくとも直訳的にジョークを残す選択もありでしょう。この選択は、 著者の意図とはまったく関わりのない、訳者による「読者の立場」の想定による判断です。
まとめますと、どの色を読者に向けるかという判断の基準となるのは、まず第一に「A:著者の意図」で、副次的に「B:読者の立場」です。この両方を 考えて、私たちはプリズムの置き方を考えなければいけないのだと思います。本末を転倒し、AをないがしろにしてBばかりを考えた訳は「勝手訳」です。逆 に、Aだけを大切にしてBを考えないのは、受け手を忘れているという意味で、コミュニケーション欠陥です。AとBが誠実に考えられた訳は、表面的に原文と どれほど離れていようと、それは立派な翻訳だと私は考えています。極端な言い方をすれば、客観的には誤訳を含んでいたとしても、です。
訳者にとっての100%は可能
「A:著者の意図」と「B:読者の立場」と書きましたが、厳密に言うと、Aは「(訳者の想定する)著者の意図」ですし、Bは「(訳者の想定する)読 者の立場」です。いずれにせよ、最後は「訳者として、伝達者としてどう捉えるか」というところで判断するしかありません。上に述べたように、客観的に見て 100%の翻訳というのは不可能かもしれませんが、訳者の判断のレベルでは、これしかない、という100%の選択がありうるのです。
翻訳をしていると、言葉が「腑に落ちる」という、という瞬間があります。著者の言葉を受け止める場面でもそういうことがありますし、読者に言葉を提 示する場面でもあります。著者側の文化への理解が深まれば深まるほど、また、想定する読者像が明確になればなるほど、そういう確信の瞬間が増えていきま す。すべてにおいてこのレベルで言葉を紡ぐのは現実的には難しいことですが、訳者の内部の世界では、努力次第で100%に近づけていくことは可能だと、私 は信じています。
実際には、著者の思いを読み違えることもあるでしょう。読者が、こちらの思ったように読んでくれないこともあるでしょう。しかし、自分が納得して訳 したものであれば、そのときには「私の判断が間違っていました」と、翻訳者として責任を引き受けることができるのです。現実問題として、世の中に「困った 翻訳」が蔓延する要因の一つに、誰も責任を引き受けられない翻訳体制、というのがあるのではないかと私は思っています(この件はまた別の機会に考えてみた いと思います)。間違いの責任は自分で引き受ける――そう言える翻訳家は幸せなのではないでしょうか。
幸い、難聴のほうはひとまず快復し、浜崎あゆみのような深刻な事態には至らずにすみそうです。再発しないよう、睡眠をじゅうぶん取るようにと医者に言われていますが、さてどうなりますことか。

